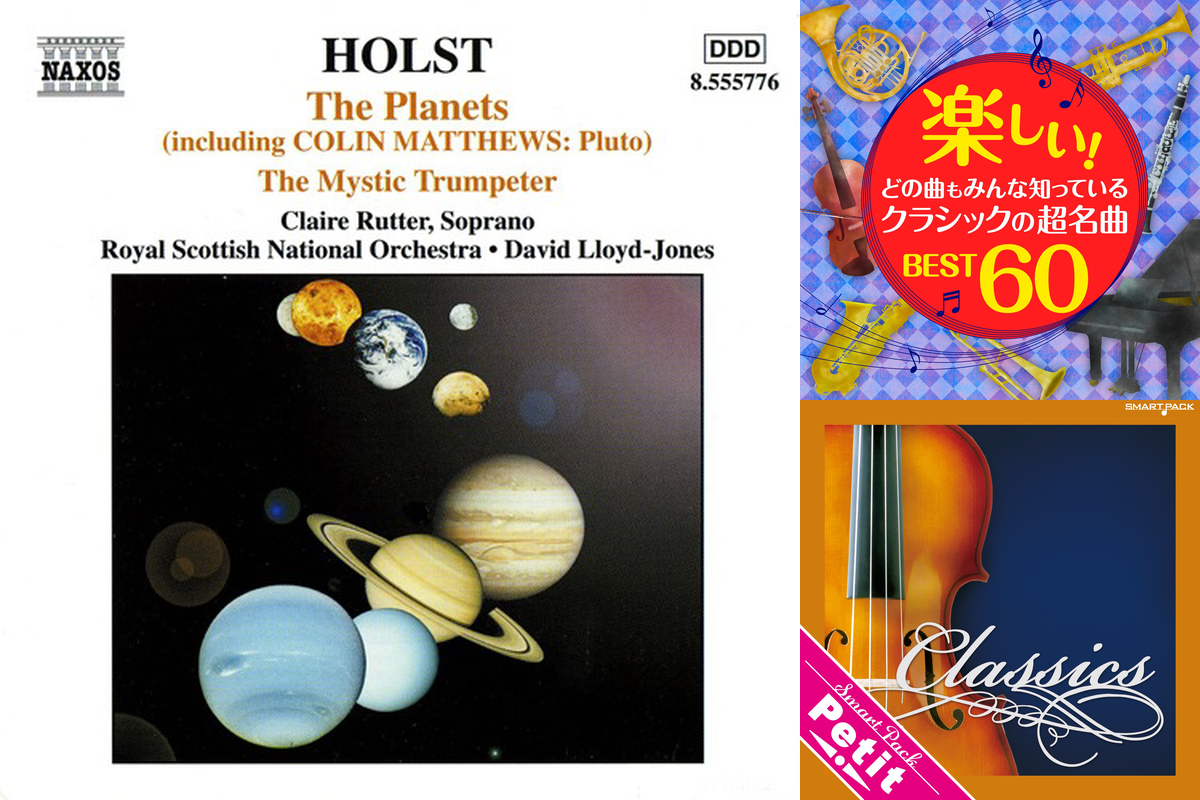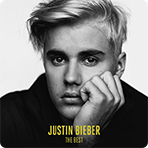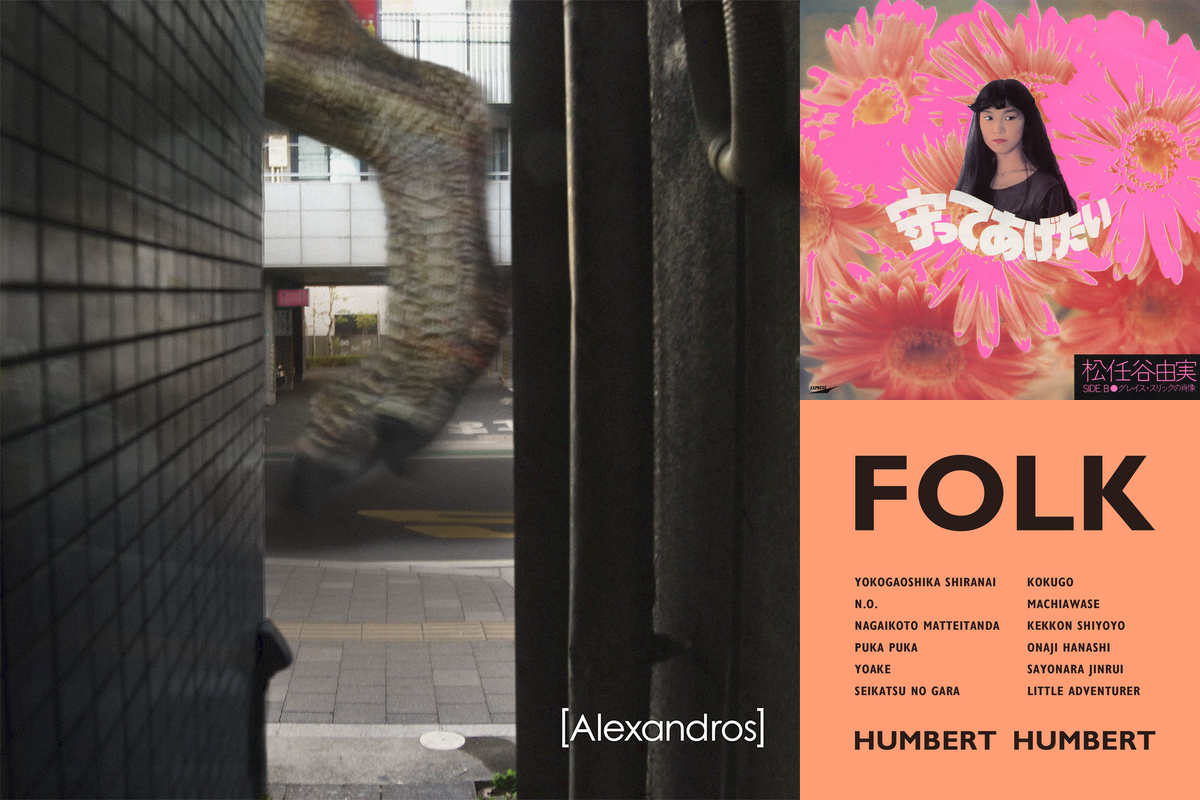普段意識してクラシックを聴く機会が少ない方でも、特定の季節に良く聴く曲や、学校の音楽授業で聴いた曲などをきっといくつかご存じでしょう。そこで今回は、AWAで聴ける曲の中から「知名度が高く、聴く機会が多く、旋律が美しい」クラシックの名曲たちを集めてみました。激しい曲や勇ましい曲でも、管弦楽やピアノの響きのせいか、なんとなく癒しが感じられるのが魅力ですね。
聴き込むほど癒されるクラシック名曲コレクション・管弦楽/オーケストラ曲編5選
ホルスト: 組曲「惑星」 Op.32 - IV. 木星 / ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団/デイヴィッド・ロイド=ジョーンズ(指揮)
冒頭の部分と、中盤のゆったり曲調が変化する部分は、BGMやCMでよく使われていて聞き覚えがある方も多いでしょう。整理整頓された広い部屋のなかで大音量で聴けば、迫力と癒しを同時に得られそうですね。クラシック曲のよいところは、少しは大きな音で聴いていてもそれほどご近所迷惑になりにくいところかもしれませんが、くれぐれも音量には注意しましょう!?
https://s.awa.fm/track/ab337b0bee5c8d59a869/
白鳥 / カレル・フィアラ/クヴィータ・ビリンスカ
フランスの作曲家、サン・サーンス作曲の組曲『動物の謝肉祭』からの1曲。『動物の謝肉祭』は、さまざまな既存曲のパロディなどを含んでいたため、サン・サーンス本人が道徳心から自身が死去するまで演奏や楽譜出版を禁じていたといういわくつきの組曲でした。しかし、この『白鳥』は何のオマージュも含まないオリジナルの楽曲だったため、彼の生前からすでに楽譜出版がされていたそう。
https://s.awa.fm/track/ee58db160df93e0e4f71/
パッヘルベル:カノン / Jorgen Ernst Hansen(Conductor)/Societas Musica Chamber Orchestra
17世紀・バロック時代の作曲家、パッヘルベルによるまさに時代をいくつも超えながら世界中で愛され続ける名曲。クラシックの父と呼ばれる大作曲家・バッハの父親とパッヘルベルは親交があり、バッハの兄に音楽指導をしていたとの記録も残っています。この曲の、3つのバイオリンで同じ主旋律を追って演奏する曲調には、聴いているうちについ瞑想の世界に入ってしまいそうな心地よさを感じますね。
https://s.awa.fm/track/744b478cb0673f137424/
プレリュードとアレグロ / 大宮臨太郎/高橋希
ピアノとバイオリン、それぞれ1台ずつというシンプルな構成で演奏される、ちょっと張り詰めたような緊迫感もあるカッコいい1曲。オーストリアの作曲家・クライスラーが20世紀に作曲しています。クラシック曲としては比較的新しめの時代の名曲にあたるのですが、斬新さよりは古典的な雰囲気を覚えますね。その理由ですが、クライスラー自身がバロック音楽に傾倒しており、そのエッセンスを多分に曲中へ盛り込んでいるからといわれています。
https://s.awa.fm/track/c544a997dabc2831c975/
エレジー(フォーレ) / 長谷川 陽子(チェロ) 藤井 一興(ピアノ)
哀愁漂うチェロの旋律が印象的なこの曲、人気TVドラマ『相棒』を見ている方ならきっと耳にしているのでは? 『相棒』の主人公である刑事・杉下右京はクラシック愛好家という設定で、さまざまな名曲がドラマの劇中でも使用されています。この曲は特にドラマの印象的なシーンでよく使われたので、強烈に覚えている方がきっと多いはず。作曲したのはフランスの作曲家・フォーレで、『ボレロ』で知られるモーリス・ラヴェルはフォーレに音楽指導を受けていたそう。
https://s.awa.fm/track/3a82a6c4cdcb3813a863/
聴き込むほど癒されるクラシック名曲コレクション・歌曲、舞台曲編6選
ワーグナー: ワルキューレの騎行 / スロヴァキア放送交響楽団
固定ファンも多いドイツの作曲家・ワーグナーによる楽劇曲『ニーベルングの指環』からの1曲。冒頭のフレーズを耳にするだけで、この曲が印象的に使われていた名作映画『地獄の黙示録』をすぐに連想する方も多いかもしれません。ちなみに『ニーベルングの指環』は、この曲を含めた全編を演奏すると、なんと4夜/計15時間にもわたってしまうという超大作です。
https://s.awa.fm/track/3ab00381ac92df262085/
《メサイア》より ハレルヤ / Alexander Vilumanis指揮/Latvian State Symphony Orchestra
12月になると聴く機会の増える曲といえば、ベートーヴェンの『第9』と並んでこの『ハレルヤ』を多くの方が思い浮かべるはず。数々のオペラの名曲で知られる作曲家・ヘンデルによるオラトリオ『メサイア』のなかの1曲です。オラトリオとは歌曲のなかでもキリスト教を題材にした「宗教劇」というジャンルを指し、この組曲のタイトルである『メサイア』はイエス・キリストを指しています。クリスマスにこの曲が街中で流れている理由が、これで分かりましたね。
https://s.awa.fm/track/9508778c9b20e5540379/
シューベルト: ます D. 550 / リンダ・ラッセル(ソプラノ)/ピーター・ヒル(ピアノ)
歌曲の王と呼ばれるオーストリアの作曲家・シューベルトが、まだ20歳の時に書いたという名曲。学校の音楽の授業で聴いたことがある方も、きっとたくさんいるでしょう。曲名の「ます」とは、もちろん川魚の鱒のこと。美しい小川のせせらぎの中を、元気よく鱒が泳いでいく様子を歌った歌詞になっています。「これだけ元気な鱒だから、釣り人に釣られるはずもないだろう」というフレーズもあり、歌詞だけ見ると童謡のような素朴さも感じられます。
https://s.awa.fm/track/9d138ca0eb86bb6d3499/
アルルの女~メヌエット(ビゼー) / Robert Heger(Violin), Marcello Rota(Conductor), Czech National Symphony Orchestra
フランスの作家・ドーデによる戯曲『アルルの女』に、『カルメン』でも知られるフランスの作曲家・ビゼーが曲をつけた劇場曲。この美しいメロディーはさまざまな場面で聴く機会がありますが、静かな曲調なのでナレーションのBGMになっていることも多いですね。ちなみに『アルルの女』の物語、てっきり主人公がアルルの女なのかと思いますが実は、農夫の男性が自分と釣り合うはずのないアルルの女に恋する…… という悲恋のストーリーなのだそう。
https://s.awa.fm/track/b5be4d7b87bbf780a916/
ボレロ(ラヴェル) / Marcello Rota(Conductor),Czech National Symphony Orchestra
あまりにも有名なこの曲ですが、フランスの作曲家・ラヴェルが1928年に作曲したバレエの楽曲です。バレエを実際にする人や観劇する人なら、この曲がどれだけバレエを踊る者にとって偉大な1曲であるかすでにご存じでしょう。1つのテーマをひたすら繰り返しながら、音量や曲調を変化させていく手法は「幼いころによく見学した工場の音がヒント」と、ラヴェル自身が語っていたそうです。
https://s.awa.fm/track/702f56afaa259bf01008/
剣の舞(ハチャトゥリアン) / Vladimir Fedoseyev(Conductor), Tchaikovsky Symphony Orchestra of Moscow Radio
ロシア(当時ソヴィエト連邦)の作曲家・ハチャトゥリアンによるバレエ楽曲『ガイーヌ』の中の、最高潮に盛り上がる場面の1節を抜粋したもの。学校の音楽の授業で聴いて、しばらく頭からこの曲が離れなかった方はきっと大勢いるはず。この曲をモチーフに作曲されたという有名な劇伴音楽もあるほど、1度聴くと忘れられないインパクトを与えてくれる1曲ですね。